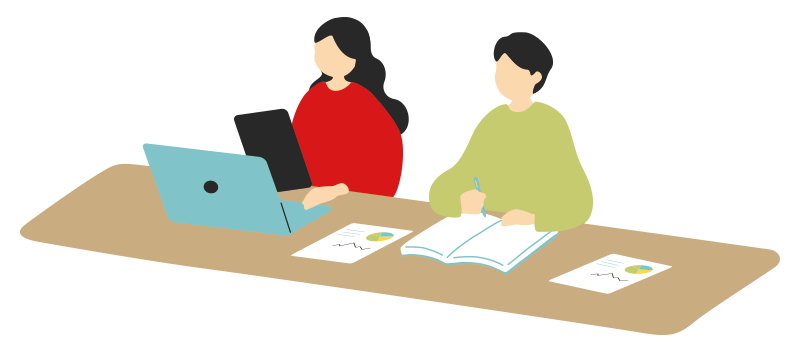研究室紹介
about us
-
日本語を教えるとは
人はことばをつかい、さまざまな人やモノ、場や情報と関わりながら生活を営んでいます。 ことばは、教室の中だけで学ばれるものではなく、日々の営みの中で多様な関わり合いを通して学ばれていきます。 つまり、日本語を教えるとは、日本語を母語としない人がそれぞれの人生において、日本語によるコミュニケーションを通じて、自ら日本語を学んでいけるような教室内外の学習環境をデザインすることであると考えられます。

-
何が起きているのかに注目する
本研究室では、まず日本語を学ぼうとする学習者一人ひとりの人生とそれぞれが生きる社会において何が起きているのかについて考えます。そして、その中でことばがどのように位置づけられ機能しているのかについて注目し理解を深めます。
そのため、大学内外において日本語を母語としない人との関わりを奨励し、その機会を創り出しています。研究室には多くの留学生を受け入れ、その中で学生は留学生のチューターやイベントの企画運営を経験するなど、研究室の環境そのものを接触、交流の場にしています。また国内外で日本語を教えている場を直接見たり、実際に教えたりする機会も提供し、学生たちはそれらの経験を通して具体的な課題や方向性を明確化します。
-
実際に教えてみる
同時に、人は、子どもから大人に至るまでにどのようにことばを学んでいるのか、これまで日本語は外国語・第二言語としてどのように教えられてきたのか、日本語とはどのような構造や体系をもったことばなのか、日本語教育とはどのような社会的役割をもつのかについて、実際に日本語を母語としない学習者を対象に日本語を教えることを通じて理解を深めます。
3年次後期には実習が行われ、実践的な教育能力養成の場となっています。本研究室で運営している本学外国人留学生や研究員を対象にした夜間日本語コースで、これまでの授業で学んだ知識やスキルを生かして実際に教えてみるだけではなく、コースの企画・運営・評価も教員とともに行い、主体的にコースに関わります。そして、自分の実習授業を録画して授業分析やディスカッションを行い、授業改善を繰り返し行います。これらのことは日本語教育とは何かを実践を通して考え、自らのことばで論じるための基盤づくりに不可欠なものです。
-
目指している人材像
本研究室では、日本語を母語としない人がそれぞれの人生において、日本語によるコミュニケーションを通して自ら日本語を学んでいけるような学習環境をデザインすることができる日本語教師を養成するだけではなく、異なる文化背景をもつ人同士の関わりに際して、互いに人として尊重し合いながら、課題を共有し、ともに解決していくための資質・能力を備えた人材の育成を目指しています。